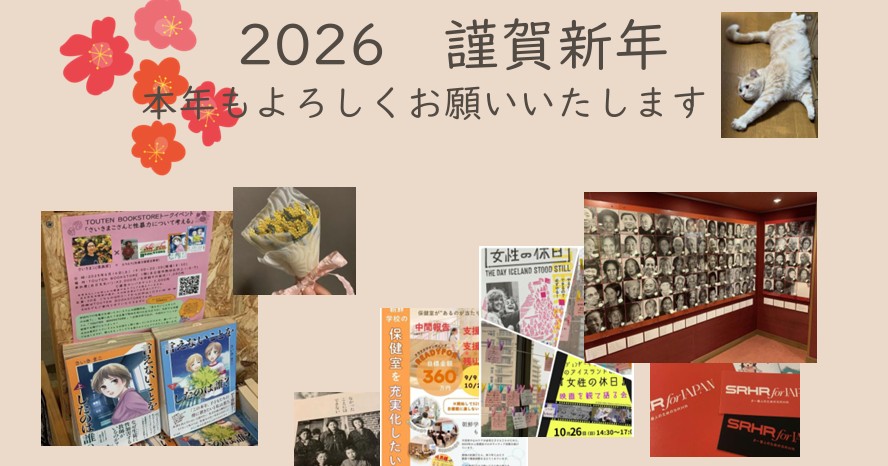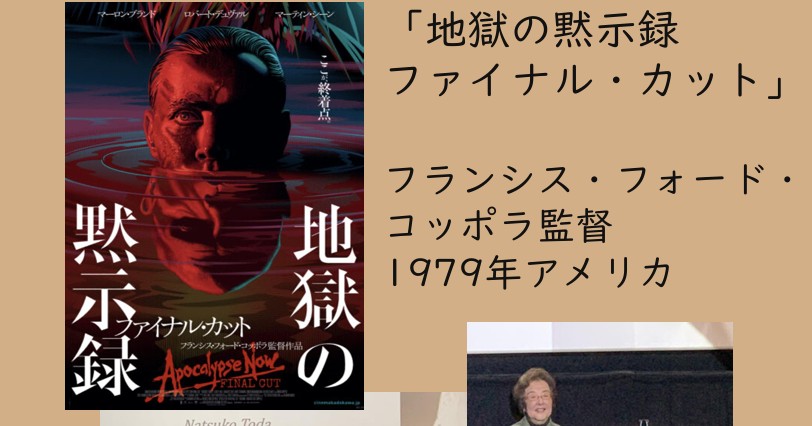大切な本93「病院で困った時、何でも相談してください。」
2024年4月に医療ソーシャルワーカー職を拝命してもうすぐ1年が経とうとしているけれど、未だに自分自身も「医療ソーシャルワーカー(MSW)」ってよくわからない。私たちの役割について、患者さんやそのご家族から求められることとは、病院内での役割とは、などととりとめもなくずーーーーーーーーーーーっと考えている。
7回にわたる新任者養成研修を受講して、県内のさまざまな病院で働かれているMSWの仲間と出会った。急性期病院、精神科病棟のある病院、終末期ケアに重点を置いている病院などなど病院といっても力を入れているところはそれぞれだし、規模や病床数、地域によっても事情はさまざま。病院というと高齢者の患者さんが多いのが一般的だけれど、私はこども病院勤務だから介護保険制度とはご縁がないし、お子さんだからこそのやりがいも難しさもたくさんある。
先を行くMSWの大先輩方の経験談が読みたくて色んな本をあたってみたけれど、同世代の方よりもちょっと先輩世代にあたる菊地かおるさんと高山俊雄さんのご著書が(今のところ)一番読みでがあった。高山さんは外国人の医療保障についても多く提言されていて、社会の中で立場の弱いマイノリティの人たちへのあたたかいまなざしが伝わってくる。
一部の想いある人だけでなく、みんなでこうした課題について考えられるようになるには、社会の成熟を待たなければならないのかな…
それから「ケア」という視点。一般的?には身体的直接的なものを思い浮かべがちだけれど、心理的なサポート、社会的なサポートまで包括的に考えると、MSWの果たす役割にも「ケア」は含まれるのかなという気づきを得られた一冊が「ケアとは何か」。
福祉を志した当初は自分が病院で働くことになるなんて思ってもみなかったし(今でもちょっと現実感がわかないところも)、医療について知らないことが多すぎて日々苦戦しまくっている。勉強不足が圧倒的な原因ではあるものの、福祉的目線が医療の現場にも必要であることは日々感じること。自分は福祉屋だから当然のようにそうした目線でいろんなことを捉えるけれど、みんながみんなそうじゃないってことを、病院に入って初めて知った…いつも自分目線でしか社会を観れていなかったと反省もしたのでした。
思いもかけないことが起こる日々の中で、個人の経験値に留めずに活かしていく方法を今模索しています。

すでに登録済みの方は こちら